
このような悩みを持っていませんか?
「働けないのは自分の甘えではないか」と感じ、自己嫌悪に陥っている。
周囲の目や評価が気になり、相談できずに一人で抱え込んでいる。
自分の状態が病気なのか、ただの怠けなのか判断できず、どうすればいいのか分からない。
「働けない自分は甘えているだけかもしれない」と感じることは、非常につらいことです。
特に、周囲の理解が得られず、自分自身を責めてしまう方も多いでしょう。
しかし、そのような思いを抱えるのはあなただけではありません。多くの方が同じような悩みを抱えています。
「働けない=甘え」ではありません。
精神的な不調や障害は、外見からは分かりにくいものですが、確かに存在するものです。
自分の状態を正しく理解し、適切なサポートを受けることが大切です。
この記事では、あなたが感じている「働けないのは甘えかも…」という不安を少しでも軽くするために、次のようなことをお伝えします。
- 働けない理由が、実は心の疲れや病気からきていることがあるというお話
- 今の自分の状態を見つめ直すための気持ちのケア方法
- 相談できる窓口や支えてくれる専門機関の紹介
この記事を読むことで、自分の状態を正しく理解し、「甘え」ではなく「必要な休息」や「治療が必要な状態」であることに気づくことができます。
そして、適切なサポートを受けることで、少しずつ前向きな気持ちを取り戻し、再び社会とのつながりを感じられるようになります。



あなたが自分自身を責めることなく、安心して次の一歩を踏み出せるよう、心から願っています。
働けないのは「甘え」?——その考えが生む心の負担


「働けない」ことを「甘え」と言う人がいますが、それは間違いです。
そうした考え方は、心の負担を大きくしてしまう原因になります。



「働けない=甘え」ではありません。
苦しんでいる人の心に、追い打ちをかけてしまいます。
- 社会の空気が「甘え」を作る
- 自分を責めてしまう人の心理
- 「働かない」と「働けない」の違い
「働けない」のには理由があります。
誰もが好きで仕事を休んでいるわけではありません。
ここでは、心の負担を軽くするために大切な考え方を伝えます。
「甘え」と決めつけてしまう社会の空気
日本では、「働くこと=当たり前」とされる風潮があります。
そのため、「働けない人=努力不足」と見られることがあります。
- 「休む=悪いこと」と考える文化
- 人と違うと「ダメ」とされがち
- 苦しみを見えづらくしてしまう
- 本音を出しにくい空気
- 声を上げることが難しい
たとえば、うつ病で動けない人がいても、外からは見えません。
ですが、そんな人に「甘え」と言ってしまえば、さらに追い詰めてしまいます。
誰でも弱ることはあります。
今は動けなくても、それがすべてではありません。
「甘え」という言葉が、どれだけ人を傷つけるか、知ってほしいのです。
あなたの「つらさ」は、本当のものです。
自分を守るためにも、他人の言葉をすべて受け止めないようにしてください。
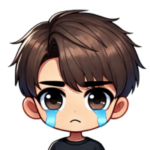
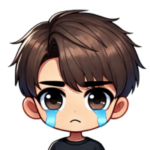
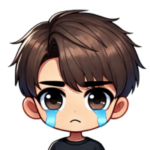
「働けない理由」を無理に説明しなくていい。
あなたの気持ちは、それだけで十分大事なものです。
自分を責めてしまう人が多い理由
働けないことで、自分を責める人はとても多いです。
それは「みんな働いているのに…」と感じるからです。
- 周りと比べてしまう
- 迷惑をかけていると思いこむ
- 「働けない自分=価値がない」と感じる
- 心の疲れを「自分のせい」と思う
- 言葉にできず、ふさぎこむ
たとえば、朝起きるのもつらいのに「働け」と言われれば、自分を責めてしまいます。
本当は、頑張りすぎて疲れているだけなのに。
体が動かないのは、心が休息を求めているサインです。
それを「自分のせいだ」と思いこむ必要はありません。
「今は休んでいい」と、自分に言ってあげてください。
回復には、まず休息が必要です。
責めることより、いたわることを大切にしてみてください。



あなたが弱いからじゃない。
つらいのは、がんばってきた証拠です。
「働かない」と「働けない」は違います
「働かない人」と「働けない人」は、まったく違います。
ですが、その違いが見えにくく、誤解されることがあります。
- 本人も「サボっているのでは」と悩む
- 周囲が理由を理解していない
- 体より心が限界のときもある
- 動けない自分に自己嫌悪
- 無理に働くと、もっと悪化する
たとえば、パニック障害やうつ病では、仕事に行こうとするだけで吐き気がすることがあります。
これは気のせいではなく、脳の機能に関係した症状です。
ですが、「サボり」だと思われてしまうと、本人はもっとつらくなります。
「働けない」は、誰にでも起こりうる状態です。
大切なのは、「なぜ働けないのか」を自分自身が知ることです。
理解しようとしない人からは、少し距離をとるのもひとつの方法です。
自分を守るために、今できることを探しましょう。



「働けない」と感じたら、それは心からのSOSかもしれません。
精神的に「働けない」と感じたとき、まず考えてほしいこと


「働きたいけど、どうしても動けない」ことは誰にでも起こり得ます。
そんなときこそ、自分の状態をじっくり見つめることが大切です。



「動けないのは甘えじゃないの?」
そう思ったら、まずは心を休める時間を持ちましょう。
- 自分の今の状態を見つめる
- 「働きたいけど動けない」理由を考える
- 専門家に相談してみる
つらい気持ちは、そのままにしておくと悪化します。
まずは「自分はどう感じているのか」を知ることが回復への一歩です。
ここでは、気持ちを整理する方法を具体的に紹介します。
今の自分の状態を見つめなおしてみる
心や体に疲れがたまると、何をする気力もなくなります。
そんなときは、自分を責めるのではなく「休むサイン」だと受け止めましょう。
- 眠れない・眠りすぎてしまう
- 食欲がない・食べすぎてしまう
- 気分が落ち込む・涙が出る
- 人と話すのがつらい
- 何も楽しめなくなる
たとえば、以前は好きだった音楽すら耳に入らなくなることがあります。
友達と話すのもおっくうで、外出するのが怖くなることもあります。
「自分が変わってしまった」と思うかもしれません。
でも、それはあなただけではありません。
多くの人が、同じように心の疲れに苦しんでいます。
まずは「今の自分の状態」を正直に受け止めてみましょう。
そこから少しずつ回復の道が見えてきます。



「今の自分」を大事にしてあげて。
それが、これから動き出す力につながります。
「働きたいのに動けない」のはなぜ?
働きたい気持ちがあるのに、体や心がついてこない。
この状態は、多くの人が体験することです。
- うつ状態で、思考が働かない
- 不安や恐怖で体がこわばる
- 自信がなく、前に進めない
- 過去の失敗がよみがえる
- 周囲の目が気になる
たとえば、電車に乗るのが怖くなる人もいます。
出社を考えるだけで、吐き気がしたり頭痛が出たりすることもあります。
そのくらい、心が追い込まれている状態なのです。
決して「怠けている」わけではありません。
心の不調は、見えにくいだけで本当につらいものです。
「なぜ動けないのか」を一人で抱えず、言葉にしてみることも大切です。
少しずつ整理していきましょう。



「働けない」には、ちゃんと理由があります。
その理由を見つけることが、次の一歩につながります。
まずは専門家(ドクター)に相談してみましょう
心の不調を感じたら、医師やカウンセラーに相談してみてください。
早めの相談が、回復を早める大きなカギになります。
- 診察を受けると安心できる
- 自分では気づけない症状がある
- 休職などの診断書も出してもらえる
- カウンセリングで心を整理できる
- 周囲にも説明しやすくなる
たとえば、心療内科では話を聞いてもらいながら治療方針を一緒に考えられます。
「何を話せばいいのかわからない」と思っても大丈夫です。
医師は、あなたの表情や声のトーンも大切な情報として受け取ります。
一人で抱えず、まずは一歩だけ勇気を出してみてください。
誰かに聞いてもらうことで、気持ちは少しずつ軽くなります。
「自分はおかしいのでは?」と思っていたことが、実はよくある症状だと知れることもあります。
その気づきが、安心と回復への第一歩になるのです。



ひとりでがんばらなくていい。
話を聞いてくれる人が、あなたの味方になります。
もし、あなたが何らかの障害を抱えているとしたら
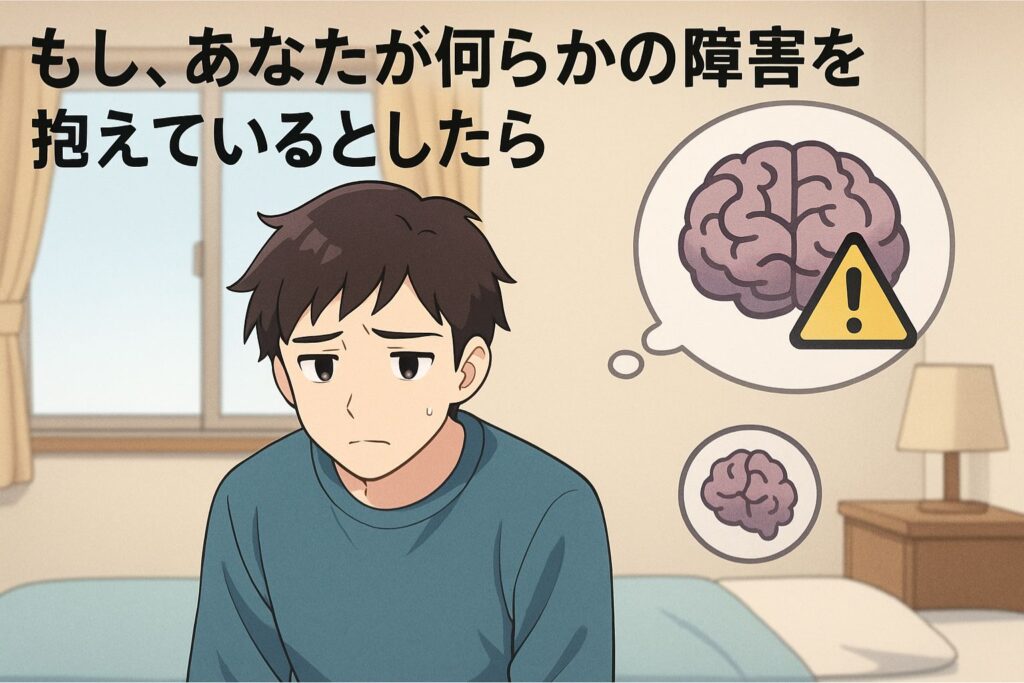
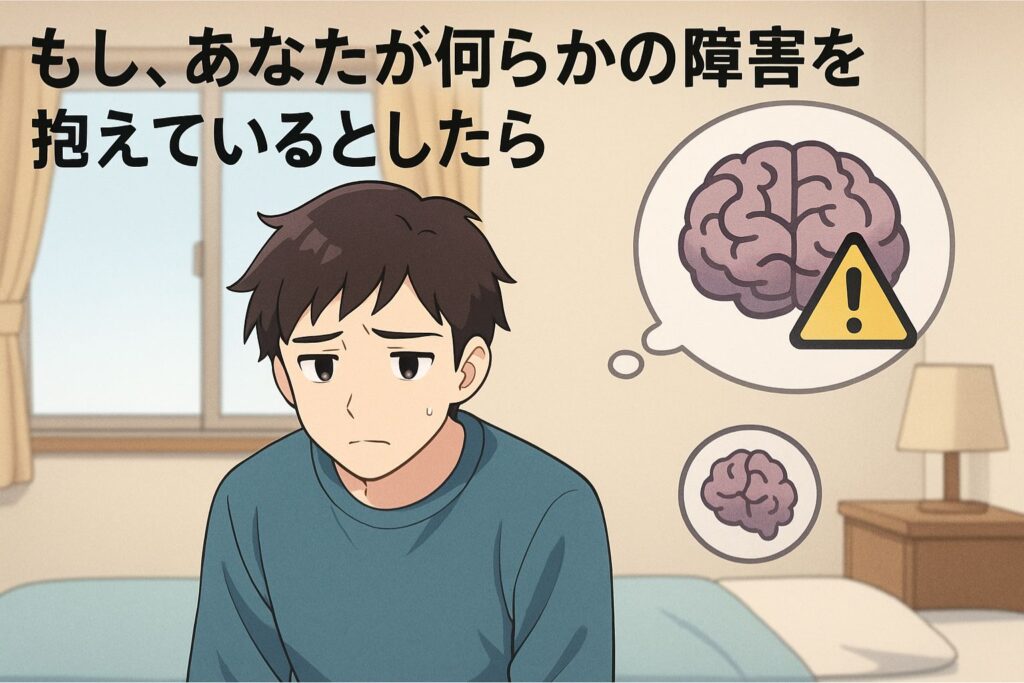
「なぜ働けないのか分からない」と悩んでいるなら、実は障害が関係している可能性もあります。
見えにくい障害は、自分でも気づかないことがあります。



「ただ自分がダメなだけ」と思っていませんか?
もしかしたら、それは障害のサインかもしれません。
- 見えにくい障害があることも
- 経験談から気づけることもある
障害というと、身体の不自由さを思い浮かべる人が多いです。
しかし、精神や発達の障害などは、外からは見えないことがほとんどです。
知らずに苦しんでいる人も少なくありません。
気づかない「生きづらさ」も障害のサインかもしれません
小さいころから「なんとなく生きづらい」と感じていた人は多いです。
それは、自分では気づかない障害のサインかもしれません。
- 人との会話が苦手
- 場の空気を読むのが苦しい
- 同じ失敗を何度もくり返す
- 急な予定変更に強いストレス
- 感覚が過敏または鈍感
たとえば、学校や職場で「普通にできること」がなぜか自分には難しかった経験はありませんか?
その原因が、自分の性格や努力不足だけだと思いこむと苦しくなります。
実は、発達障害やHSP(敏感すぎる気質)など、目に見えない障害の可能性もあるのです。
早くに気づくことができれば、適切な支援を受けられます。
「どうしてできないのか」に理由があると分かるだけで、心が少し楽になります。
もし気になることがあれば、発達検査などを受けてみてもよいでしょう。



「できない」には、ちゃんと理由があります。
あなたの苦しみは、見えない障害かもしれません。
他の人の経験談から見える「気づき」もあります
同じように悩んできた人の話を聞くと、「自分だけじゃない」と感じられます。
経験談は、自分の気づきや希望につながるヒントにもなります。
- 障害に気づくまでのエピソード
- 診断を受けて楽になった話
- 支援を利用して働けるようになった
- 家族や周囲の理解が得られた
- 「自分らしく」働く方法が見つかった
たとえば、ある人は「自分のこだわりが強すぎる」と思っていたのが、発達障害の特徴と知って気持ちが楽になりました。
また、別の人は「仕事が長続きしない」のが、HSPによる感覚過敏だったことに気づき、適職に出会うことができました。
障害に気づいたことで、無理をせず、自分に合った働き方を選べたという声も多いです。
こうした経験談からは、「自分の問題だと思っていたことが実は違った」という気づきが得られます。
あなたにも、気づくことで変わる未来があります。
今はつらくても、少しずつ自分を知ることで、道が開けていくでしょう。



経験談は、自分を知るヒントです。
あなたの「気づき」も、きっと見つかります。
「働けるようになる」ための考え方と方法
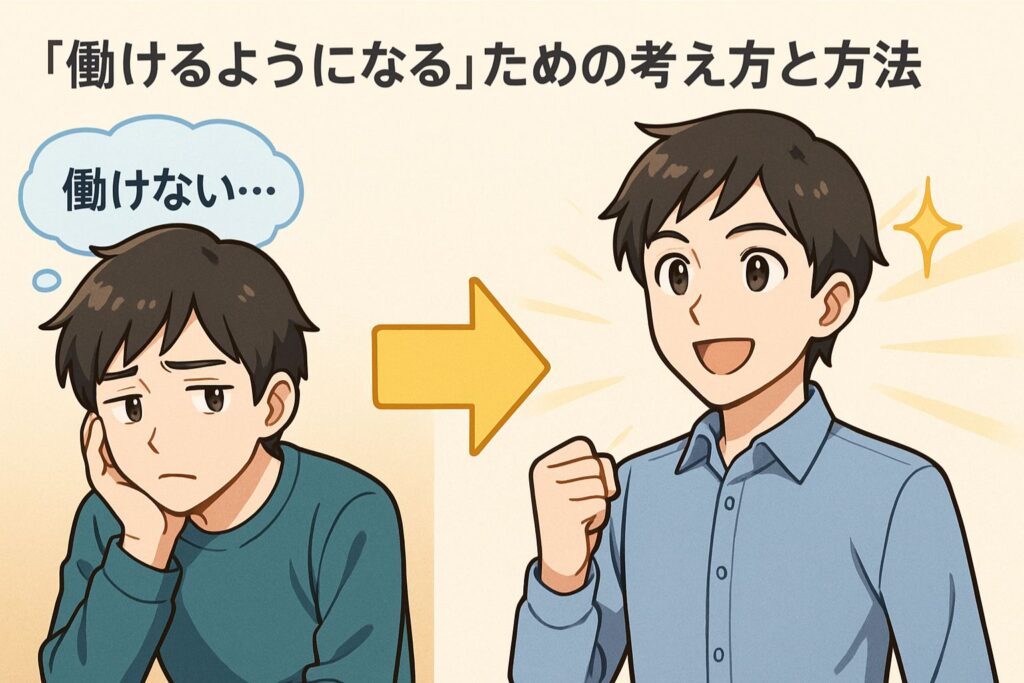
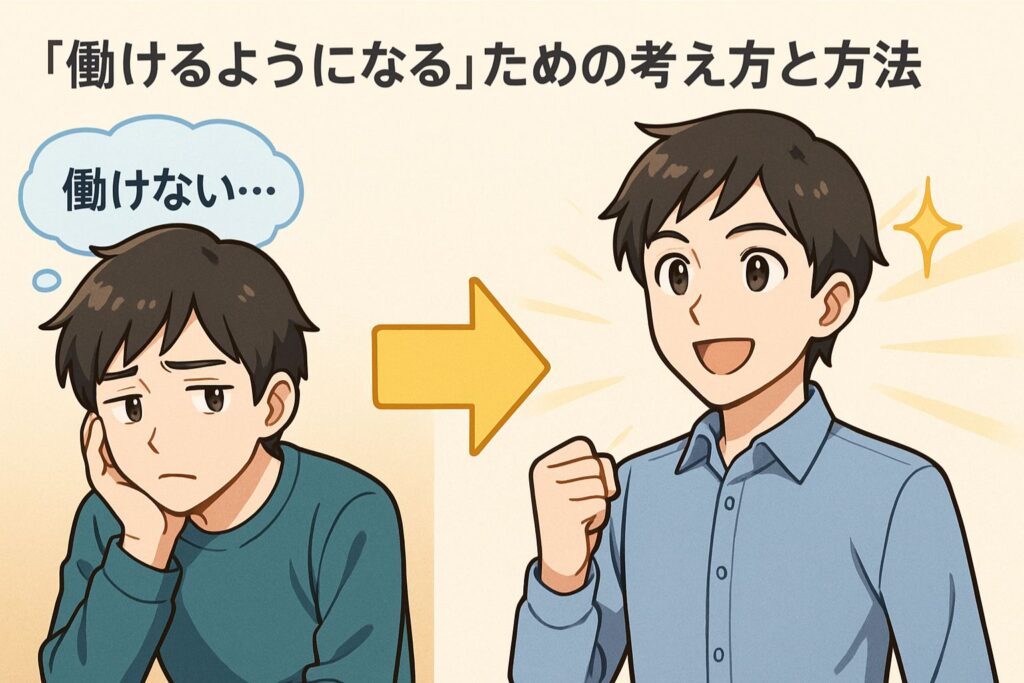
「働けない」状態から少しずつ「働けるかもしれない」状態に近づくことはできます。
そのためには、焦らず自分に合った方法で進むことが大切です。



いきなりフルタイムじゃなくても大丈夫。
あなたのペースで進めばいいんです。
- 誰かに相談することが第一歩
- 自分に合った働き方を考える
- 少しずつ動く練習をする
- 就労移行支援という制度を活用する
働くことはゴールではありません。
あなたが「自分らしく生きる」手段のひとつとして、今できることを見つけていきましょう。
解決の糸口は、誰かに相談することから
「働けない」と感じたとき、まず相談できる相手がいるかどうかが大切です。
信頼できる人に話すことで、気持ちが整理され、自分の状態にも気づきやすくなります。
- 家族や友人に話してみる
- 支援団体の窓口を使う
- 医師やカウンセラーに相談
- 地域の就労支援機関を活用
- SNSやオンライン相談を使う
たとえば、「自分ではどうしていいか分からなかったけど、友達に話すだけで気持ちが軽くなった」という声は多いです。
悩みを言葉にすることで、自分でも気づいていなかった本音に出会えることがあります。
また、就労移行支援のような専門機関では、同じ悩みを持つ人たちが集まっており、安心して相談できます。
「働きたいけど、まだ不安」という声に耳を傾けてくれる支援者もたくさんいます。
話すことは勇気がいるかもしれませんが、一歩を踏み出せば状況が変わる可能性があります。
まずは「聞いてくれる人」がいる場所を探してみましょう。
相談は、未来を変える第一歩です。



誰かに話すだけで、心がふっと軽くなることもあります。
自分に合った働き方を見つけるには?
「働く」といっても、フルタイムだけが選択肢ではありません。
自分に合った働き方を見つけることが、無理なく社会とつながる一歩になります。
- 短時間勤務から始める
- 在宅ワークを検討する
- 自分の得意を活かす
- スモールステップで進む
- 障害者雇用なども視野に
たとえば、パートやアルバイトなどの短時間勤務は、体調を見ながら無理なく始めやすい方法です。
最近では、クラウドワークスやランサーズのような在宅の仕事も増えており、自分のペースで働く選択肢も広がっています。
また、「得意なこと」「苦にならないこと」を洗い出してみると、自分に向いた仕事が見えてくることもあります。
「好き」や「できそう」から始めてみるのも、一つの方法です。
障害者雇用枠を利用すると、配慮を受けながら働くことも可能になります。
まずは、いくつかの選択肢を知り、「どれが自分に合いそうか」を考えてみてください。
すぐに答えが出なくても、考えること自体が第一歩です。



「どんな働き方なら続けられそう?」
そう問いかけることから始めてみましょう。
時間をかけながら回復し、少しずつ働く方法
無理にすぐ働こうとせず、「回復しながら少しずつ」が大切です。
焦らず、自分のペースで社会とつながる準備をしていきましょう。
- まずは生活リズムを整える
- 体調と心を安定させる
- 短時間の活動から始める
- 家事・買い物などから練習
- 週1日からでもOK
たとえば、「午前中だけ散歩に出てみる」「毎日同じ時間に起きて朝ごはんを食べる」といった小さな行動も、立派な一歩です。
そこから少しずつ、図書館に行く、カフェに行ってみる、人と話してみるなど、外の世界に慣れる練習をしましょう。
家の中でできる仕事や、オンラインの活動にチャレンジするのも良い方法です。
また、週1日だけ何かに取り組むことからスタートするのもおすすめです。
疲れた日は思いきって休むことも大切です。
「自分を大切にしながら働く」ために、準備の時間を惜しまないでください。
ゆっくりでいいんです。



がんばるより、「ゆっくり戻る」が大事。
一歩ずつ、少しずつで大丈夫です。
就労移行支援事業所という選択肢を知っていますか?
「働きたいけど不安がある」「自信がない」という人にとって、就労移行支援は心強い味方になります。
就労をめざす障害のある人が、安心してステップアップできる場所です。
- 障害のある人の就職支援施設
- 生活リズムや社会性もサポート
- 職業訓練や就活練習ができる
- 就職後の定着支援もある
- 費用はほとんど無料
たとえば、生活リズムが崩れていた人が、事業所に通うことで朝起きる習慣がつき、毎日笑顔が増えたという事例があります。
他にも、人と話すのが苦手だった方が、訓練を通じて会話ができるようになったという声もあります。
事業所では、パソコンの練習や履歴書の書き方、模擬面接なども受けられます。
スタッフや仲間に支えられながら、自信を取り戻していける場所なのです。
また、就職後もフォローを受けられるため、「就職したら終わり」ではなく、「安心して働き続けられる」サポートがついてきます。
費用は自治体が負担するため、自己負担はほとんどないことが多く、経済的な負担を心配する必要もありません。
まずは「見学だけでもOK」です。



あなたの「働きたい」を応援する場所があります。
ひとりで悩まず、まずは見に行ってみませんか?
就労移行支援事業所の紹介


就労移行支援事業所は、「働きたいけれど不安がある」人のためのサポート施設です。
安心できる環境の中で、自分のペースで働く準備ができる場所です。



「仕事のこと、誰に相談すればいいの?」
そう感じたら、まずは就労移行支援事業所を知ってみてください。
- どんな支援を受けられるのか
- 事業所でのサポート内容
- 利用者の変化と活動内容
この章では、実際にどんな支援が受けられるのか、どんな雰囲気の中で活動しているのかを詳しく紹介します。
まだ見たことがない人でも、イメージがわきやすくなるはずです。
就労移行支援とはどんな支援なのか
就労移行支援は、一般企業への就職を目指す障害のある人を対象にした福祉サービスです。
「いきなり働くのは不安…」という人でも、段階的にスキルを身につけていくことができます。
- 障害がある18歳〜65歳が対象
- 最大2年間の利用が可能
- 個別支援計画に沿って訓練
- 企業見学・実習ができる
- 就職後の職場定着支援あり
たとえば、ある事業所では「通所が週1日からOK」という柔軟な対応をしているところもあります。
また、「午前だけ」「午後だけ」など、自分に合った時間帯で通うこともできます。
医師の意見や本人の希望をふまえて、無理のない支援計画が立てられるのも安心ポイントです。
職員との面談を通じて、気持ちの整理をしながら、将来について一緒に考えていきます。
「はたらくってなんだろう」から始めてOKなのが、就労移行支援の魅力です。
就職に向けた最初のステップとして、心の居場所にもなります。



最初は「話すだけ」でも大丈夫。
そこから少しずつ未来が動き出します。
事業所で受けられる具体的なサポート内容
就労移行支援事業所では、ただ「通うだけ」ではなく、働くために必要な準備をしっかり行えます。
生活面から仕事のスキルまで、幅広いサポートが受けられるのが特徴です。
- 日常生活の安定サポート
- ビジネスマナーの習得
- パソコンなどの訓練
- 面接練習や履歴書作成支援
- 職場見学・実習の機会
たとえば、「朝起きるのが苦手」という方には、決まった時間に通所することで生活リズムを整えるサポートが行われます。
ビジネスマナー講座では、言葉遣いや電話対応なども練習できます。
パソコン訓練では、WordやExcelの基本操作から学ぶことができ、在宅ワークへの準備にもなります。
模擬面接や履歴書の添削も丁寧にサポートしてもらえるので、就職活動への不安が少なくなります。
さらに、実際の職場を見学したり、短期間働いてみる「企業実習」も体験できます。
こうした経験を通じて、「自分にできそうな仕事」を探すことができるのです。
ただ座学で終わらず、実践的に学べるのが大きなポイントです。



「働けるかな…?」
その気持ちに寄り添いながら、一歩ずつ力をつけられます。
実際の事業所活動と利用者の変化
就労移行支援事業所に通い始めると、少しずつ心と体に変化があらわれます。
最初は不安だった人たちも、段階的に笑顔と自信を取り戻していくのです。
- 朝起きられるようになった
- 人と話すのが楽になった
- 毎日通えるようになった
- 新しいスキルが身についた
- 就職できた人もいる
たとえば、ある女性は「朝が苦手で何度も寝坊していた」と言います。
でも、事業所に通ううちに、決まった時間に起きるリズムが身につき、今では毎朝自然に目が覚めるようになったそうです。
別の男性は、「人と会話するのが怖くて引きこもっていた」経験があります。
ですが、グループワークで少しずつ人と話す機会が増え、次第に雑談ができるようになりました。
また、就労実習に参加したことで、「自分にも仕事ができる」と思えるようになり、就職にもつながったという声もあります。
大きな変化は、小さな成功の積み重ねから生まれます。
事業所では、その小さな一歩をたくさん応援してもらえるのです。
「ひとりでは難しいこと」も、環境と支援があれば可能になります。



ちいさな成功体験が、あなたの自信につながっていきます。
代表的な就労移行支援事業所3選
ウェルビー(Welbe)|高い就職者を誇る就労移行支援事業所


ウェルビー(Welbe)は、障害者の一般就労をサポートする就労移行支援事業所です。
精神障害、発達障害、知的障害、身体障害など、さまざまな障害を持つ方に対応し、全国に121の事業所を展開しています。
就職支援の実績は非常に高く、2024年度の就職数は1,165名、就職後の定着率も91%とトップクラスの水準です。
ウェルビーでは、個別の支援計画を作成し、ビジネスマナーやPCスキルの習得、職場実習、面接対策など、就職に必要なスキルをトータルでサポート。
さらに、就職後も職場への定着支援を続け、働き続ける力をしっかりサポートしてくれます。
また、希望者にはお弁当支給で生活支援にも配慮しています。
まとめ|ウェルビーはこんな人におすすめ
- 事務職や未経験職種にもチャレンジしたい方
- 個別に手厚いサポートを受けたい方
- 精神障害・発達障害など特性に合った支援を受けたい方
- 高い就職率・定着率の実績がある事業所を選びたい方
ココルポート(cocorport)|個別支援にこだわっている就労移行支援事業所


ココルポート(cocorport)は、首都圏・関西・東海・福岡等にに81の事業所を展開しています。
就職者数は、2023年度が762名、累計4,803名、さらに就職後の職場定着率は90%以上という高い実績を誇ります。
ココルポートの最大の特徴は、「個別支援に徹底的にこだわっている」ことです。
利用者一人ひとりの特性や希望に合わせたオーダーメイドの支援プログラムを提供し、安心して訓練に取り組むことができます。
また、経済的な不安を抱える方でも安心して通えるよう、昼食支給や交通費補助といった支援制度も整備されています。
まとめ|ココルポートはこんな人におすすめ
- 発達障害・精神障害に特化した支援を受けたい方
- 高い職場定着率を重視したい方
- 個別に寄り添ったサポートを希望する方
- 就職後も安定して働き続けたい方
ミラトレ|大手パーソルグループ運営の就労移行支援


ミラトレは、障害のある方を対象に、一般企業への就職を支援する就労移行支援事業所です。
運営は、総合人材サービス大手のパーソルグループ(dodaやanなどを手掛ける企業)が行っています。
精神障害、発達障害、知的障害、身体障害、難病など幅広く対応し、全国に約15拠点を展開しています。
ミラトレの最大の特徴は、
- doda(転職サイト・エージェント)との連携による豊富な求人情報
- 企業実習型プログラムの充実
- 就職率95%超
という、就職直結型の支援体制です。
ビジネスマナー、PCスキル、グループワーク、企業実習などを通じて、即戦力としてのスキルを身につけることを重視しており、就職後も職場定着支援を手厚く行っています。
また、ミラトレは就職後の半年定着率が97%と、全国平均(約60%)を大きく上回る高水準を誇ります。
まとめ|ミラトレはこんな人におすすめ
- できるだけ早く一般企業に就職したい方
- 大手企業・上場企業への就職も視野に入れたい方
- 企業実習を通じて実践的な経験を積みたい方
- 定着支援までしっかりしている事業所を選びたい方
まとめ:「働きたくない」のではなく「働けない」だけかもしれない
「働きたくない」と思っているのではなく、実は「働けない状態」にあるだけかもしれません。
まずは、その違いに気づくことが、自分を守る一歩です。



あなたは「さぼっている」のではありません。
心と体が、今「休みたい」と言っているのです。
- 「働けない」自分を責めすぎない
- 社会の中に自分の居場所はある
- 働き方はたくさんある
つらいときは、まず休んでください。
そのあとで、「自分には何ができそうか」「何が向いていそうか」を、ゆっくり考えればいいのです。
選べる働き方は、今の時代たくさんあります。
「働けない」自分に意味をつけすぎないで
「働けない自分はダメ」と思いこまないでください。
今は回復のために必要な時間を過ごしているだけです。
- 他人と比べないでいい
- 弱っているときこそ自分を大事に
- 「今」を否定しなくていい
- 休むことにも意味がある
- 人にはそれぞれ違うペースがある
たとえば、木も花も季節ごとに休む時期があります。
人間だって、同じように「今は休むとき」もあるのです。
「意味のある休み」なんて言葉は必要ありません。
ただ「休んでいるだけ」で、十分価値があります。
自分にとって今必要なことを、信じてあげてください。
それがあなたの強さにつながっていきます。



意味をつけなくていい。
「休んでる」それだけで、あなたはえらい。
社会の中に、自分らしい居場所がきっとある
今は見つからなくても、あなたに合った居場所はきっとあります。
それは職場だけでなく、地域、仲間、オンラインなど、いろいろな形で存在しています。
- 自分のことを受け入れてくれる場所
- 話を聞いてくれる人がいる環境
- 無理せず参加できる活動
- 同じ悩みを持つ人たちの集まり
- あなたを必要としてくれる場
たとえば、就労移行支援事業所もそのひとつです。
「がんばらなくていい」「話すだけでもいい」そんな場所が、全国にあります。
家の中でも、誰かの声を聞くだけで救われることもあります。
オンラインでもリアルでも、あなたを受け入れてくれる場所は必ず見つかります。
「ここにいてもいい」と思える場所に、いつか出会えるはずです。
そのために、今は自分をいたわる時間にしてください。



あなたの「居場所」は、もうすぐ見つかります。
働き方は一つじゃない。あなたに合った方法があります
「正社員じゃなきゃいけない」「フルタイムでないと…」そんな思い込みは捨てて大丈夫です。
今の時代、いろんな働き方があります。あなたに合う形で関われば、それでいいのです。
- 短時間パートでもOK
- 在宅ワークや委託も選べる
- ボランティアから始めてもいい
- 障害者雇用の枠も活用できる
- あなたらしく働ける形がある
たとえば、週2日、午前中だけ働いて、午後は休む生活をしている人もいます。
また、在宅で得意なデザインやライティングの仕事を続けている人もいます。
「あなたに合った働き方」は、実は思っているよりたくさんあります。
いちど、就労移行支援事業所などに相談してみることで、知らなかった選択肢に出会えるかもしれません。
「こうしなければいけない」を手放して、自由に未来を考えてみましょう。
あなたの「これならできそう」が、きっと見つかります。



あなたらしく、あなたのペースで。
それが一番の働き方です。
