
このような悩みを持っていませんか?
自分が就労移行支援の対象者に該当するのかがわからない。
年齢や障害の程度が利用条件に合致しているのか不安。
障害者手帳を持っていないが、利用できるのか疑問。
「再び働きたい」という思いが芽生えても、制度の複雑さや情報の不足から、一歩を踏み出すのは容易ではありませんよね。
年齢や障害の程度、手帳の有無など、さまざまな条件が頭をよぎり、不安になるお気持ち、よくわかります。
この記事では、就労移行支援の対象者に関する情報をわかりやすく解説し、あなたの不安を解消するお手伝いをします。
制度の概要から具体的な条件まで、丁寧にご説明しますので、安心して読み進めてください。
- 就労移行支援の仕組みと利用対象者の条件
- 精神・発達・知的・身体障害や難病のある人への具体的支援内容
- 利用開始までの流れや必要な手続き、費用の仕組み
- 見学・相談から始められる安心の利用方法と成功事例
この記事を読むことで、就労移行支援の対象者に関する疑問が解消され、自信を持って次のステップに進むことができます。
再就職への道が明確になり、安心して新たな一歩を踏み出せるようになります。



あなたの「働きたい」という思いを大切に、この記事がその実現への一助となれば幸いです。



一緒に、明るい未来への第一歩を踏み出しましょう。
就労移行支援とは?まずは基本を解説


就労移行支援とは、障害や難病のある人が一般企業で働くために支援を受けられる福祉サービスです。
就職に必要なスキルや生活の安定をサポートするのが特徴です。



働きたいけど自信がない人にとって、就労移行支援は安心して社会に出る第一歩になります。
- 就労移行支援の目的と役割
- 障害福祉サービスの中での位置づけ
- 一般就労と福祉的就労(就労継続支援)の違い
働きたいという気持ちがあっても、一人では踏み出しにくい人にとって、サポート体制があることは大きな安心材料になります。
国の制度に基づいて提供されているため、利用者の負担も少なく、誰でもチャレンジしやすい仕組みが整っています。
ここからは、就労移行支援の目的や制度の中での位置づけ、他の就労支援との違いをわかりやすく見ていきましょう。
就労移行支援の目的と役割
就労移行支援の目的は、障害や難病を持つ人の「働く力」を育て、一般企業への就職を実現することです。
一人ひとりの状況に合わせて、就職に必要な準備や支援を提供するのが特徴です。
就職だけでなく、長く働き続けることも視野に入れてサポートします。
- 生活リズムを整える支援
- 職場に必要なスキルを学ぶ
- 就職活動のサポート
- 就職後の定着支援もある
たとえば、双極障害で休職が続いていた人が、就労移行支援の生活訓練やPC訓練を受けて、自信を取り戻していきました。
最初は週2日からスタートし、徐々に週5日通所ができるようになりました。
その後、履歴書の添削や面接練習を受けて、自分に合った職場に就職することができました。
このように、就労までの道のりを支えてくれるのが就労移行支援です。
はじめての就職や、再チャレンジを考えている方には心強い制度です。



就職に不安がある人でも、支援を受けながら一歩ずつ前に進むことができます。
障害福祉サービスの中での位置づけ
就労移行支援は、障害者総合支援法に基づく福祉サービスのひとつです。
通所型の就労系サービスとして、国が支援しています。(近年では、在宅系のサービスも増えています。)
生活訓練や就労継続支援と並ぶ、重要な支援制度です。
- 障害者総合支援法に基づく制度
- 一般就労を目指す支援
- 通所型で3年まで利用可能(原則2年間)
- 対象者は原則18〜64歳
同じ障害福祉サービスでも、「生活介護」や「居宅介護」は日常生活を支えるもので、就労移行支援は仕事への橋渡しです。
福祉サービスの中でも、より「働くこと」に特化した仕組みであることがわかります。
行政や医療機関とも連携して支援が行われるため、安心して利用できます。
一般就労と福祉的就労(就労継続支援)の違い
一般就労は企業に直接雇用される働き方で、福祉的就労は支援付きで働く形です。
就労移行支援は、福祉的就労から一般就労へつなぐステップとして位置づけられます。
それぞれの人に合った働き方を選ぶことが大切です。
- 一般就労は企業に雇用される
- 福祉的就労は支援付きで働く
- 就労移行支援は移行のための準備
- どちらにもメリットがある
たとえば、知的障害のある方が福祉的就労で働きながらスキルをつけ、最終的に一般企業に採用された事例もあります。
一方で、体調や障害の特性から、福祉的就労を長く続ける選択もあります。
どちらが良いということではなく、自分に合った働き方を見つけることが大切です。
就労移行支援は、選択肢を広げる大事な支援です。
働くことに不安がある人でも、一歩ずつ支援を受けながら前に進めます。



就労移行支援は、「働きたい」を支える場所です。
対象者はどんな人?就労移行支援の利用条件
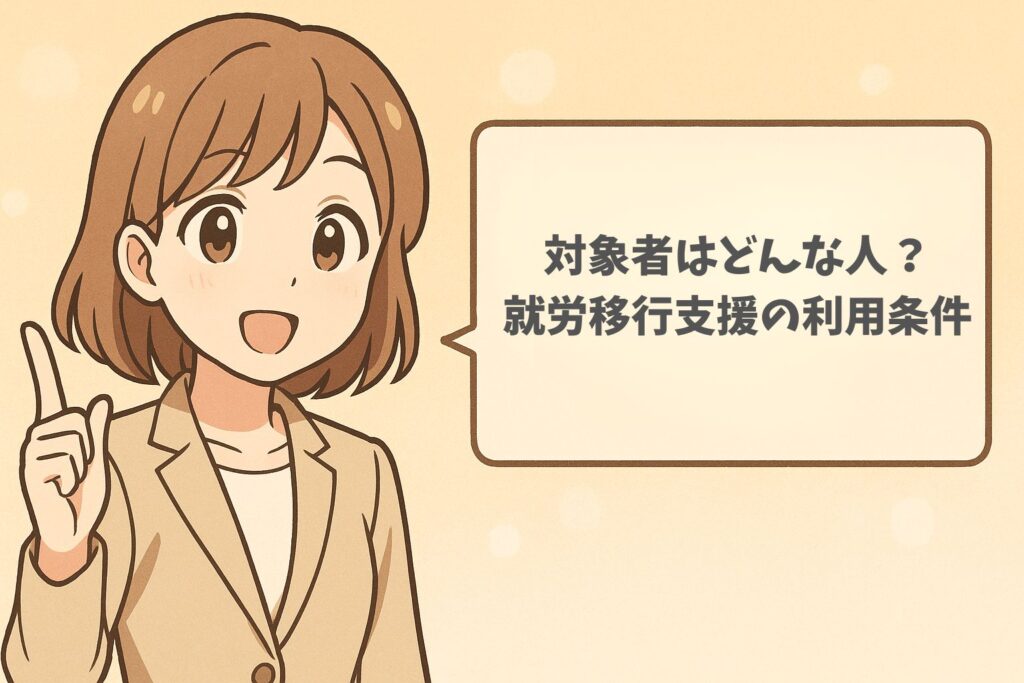
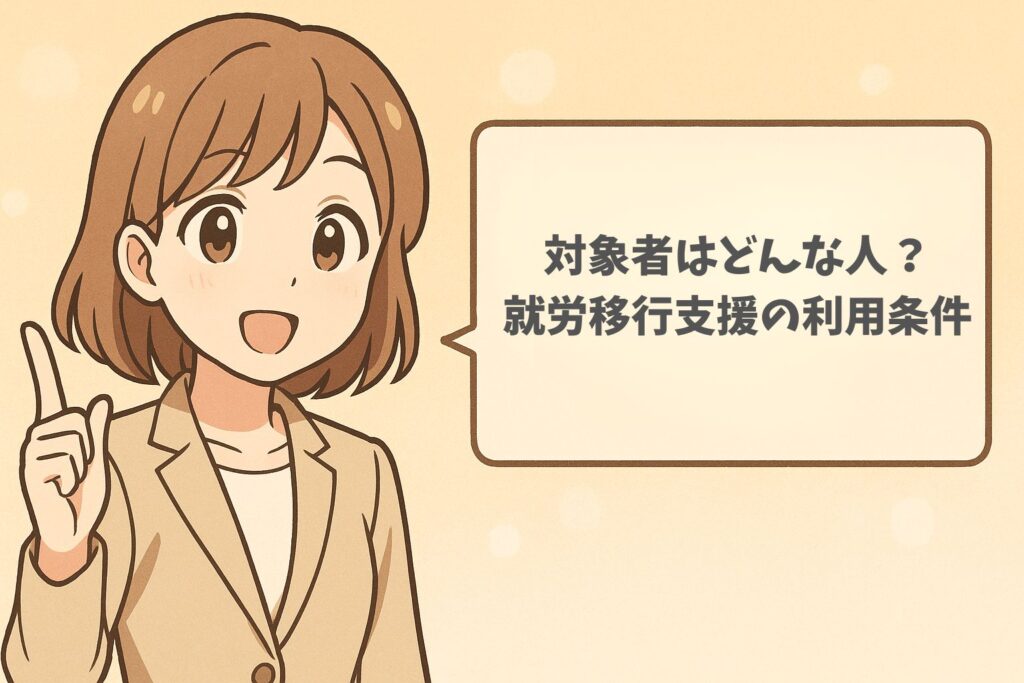
就労移行支援は、障害や病気で働きづらさを感じている人が対象です。
手帳の有無に関わらず、医師の意見書や市町村の判断で利用できる場合もあります。



「障害が軽いからダメ」と思わず、まずは相談してみることが大切です。
- 就労移行支援の対象になる人とは
- 利用できる年齢:65歳未満が原則
- 障害者手帳がなくても利用できる場合とは
- 難病のある方も対象になる?
- 医師の診断書が必要な場合の対応
利用条件は自治体の判断も大きく関わりますが、医師や相談員の助言で広く対応してもらえることが増えています。
ここからは、実際に対象となる人や利用の条件について詳しく見ていきましょう。
就労移行支援の対象になる人とは
対象は、一般企業での就職を希望し、支援を受けながら働く準備をしたい人です。
身体・知的・精神・発達障害、難病のある人など、幅広く対応しています。
手帳の有無に関わらず、困りごとがあるなら対象になる可能性があります。
- 障害のある18〜64歳の人
- 就職を目指す意思がある
- 福祉的支援が必要と判断された人
- 自治体が支給決定した人
たとえば、うつ病の回復期にある人が、通院しながら週3日から通所を始め、体力と自信をつけていきました。
支援を受けながら生活を整え、半年後には一般企業に就職できました。
このように、完治していなくても「働く意思」があれば対象になります。
就労意欲はあるけど不安が強い人にもおすすめです。



「働きたいけど今は自信がない」という人が、少しずつ前向きになれる支援です。
利用できる年齢:65歳未満が原則
就労移行支援の対象年齢は、原則18歳から64歳までです。
65歳以上になると、新規での利用はできません。
ただし、すでに利用していた場合は、継続利用が認められることもあります。
- 利用開始は18歳以上
- 65歳未満が原則
- 65歳到達前の継続利用は相談可
- 障害者雇用促進法にも連動
たとえば、63歳で就労移行支援を開始した方が、支援を受けながら翌年に就職を果たしたケースもあります。
この方は、その後も同じ職場で長く働き続けています。
「年齢が高いから無理かも…」と思わず、まずは市町村に相談してみましょう。
例外や特例に対応してくれることもあります。



年齢だけであきらめるのは、もったいないです。
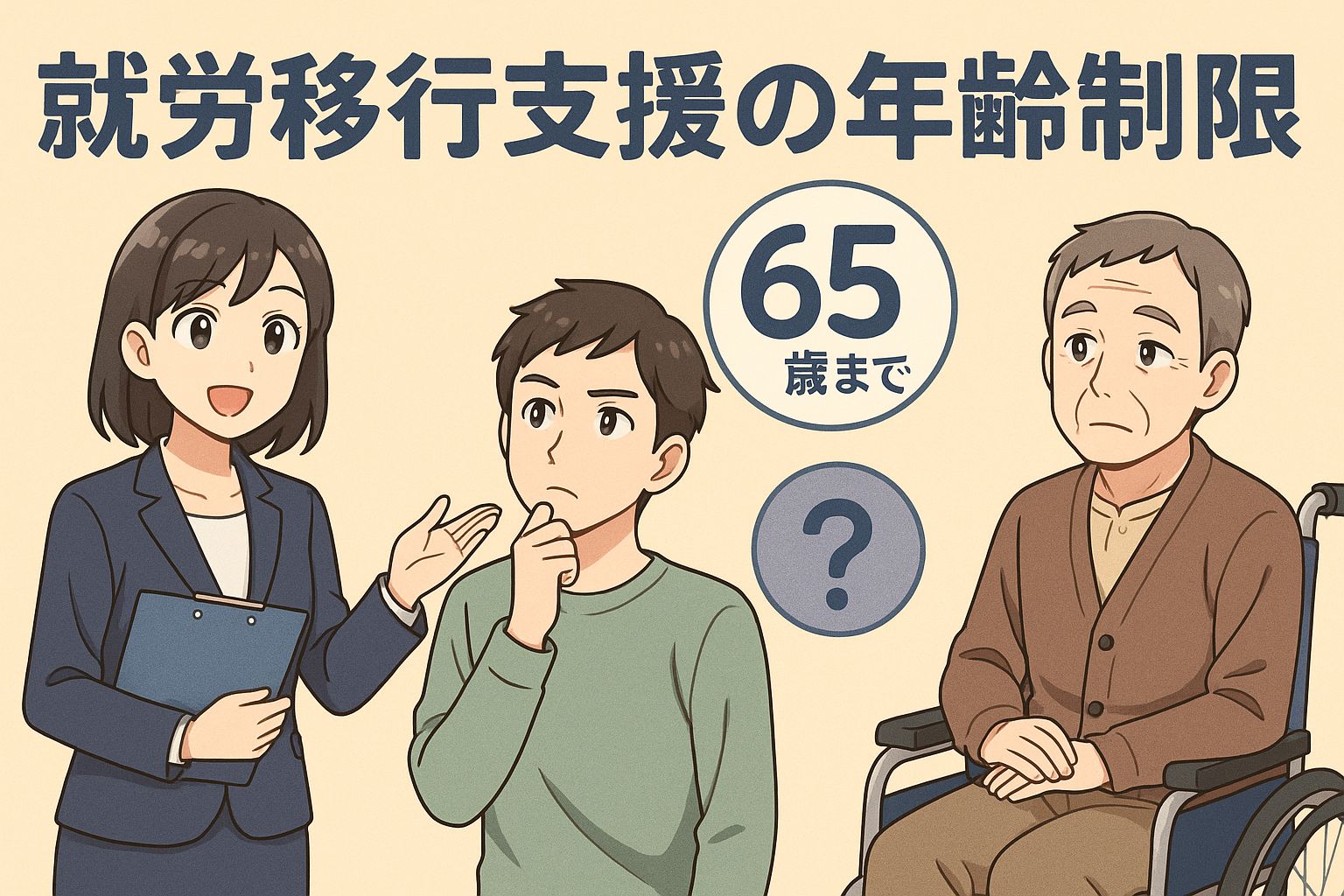
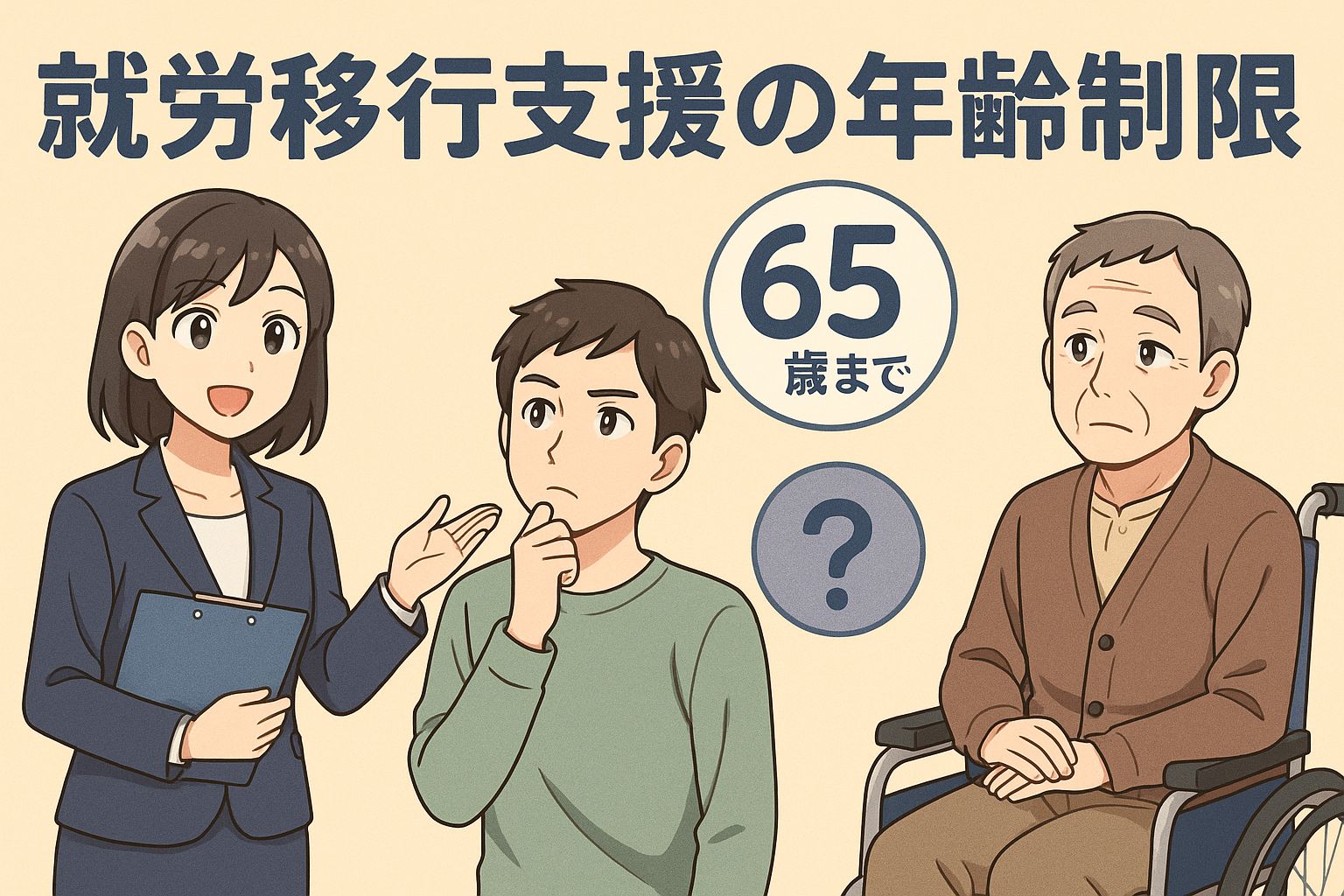
障害者手帳がなくても利用できる場合とは
障害者手帳がなくても、医師の診断や意見書があれば利用できるケースがあります。
市区町村が「福祉的支援が必要」と判断すれば、サービス利用が認められるのです。
特に精神疾患のある人に多く見られるケースです。
- 手帳がなくても診断があれば対象
- 医師の意見書を提出する
- 市町村が必要と判断すれば利用可
- 精神疾患での利用が多い
たとえば、うつ病で手帳を持っていなかった人が、医師の意見書をもとに就労移行支援を開始しました。
生活のリズムを整えながら、就労に向けた準備ができたことで、半年後に再就職を果たせました。
手帳の取得には時間がかかることもありますが、まずは医師の診断と相談が大切です。
「手帳がない=利用不可」ではないと知っておきましょう。
気になる方は医師や自治体に相談してみてください。



障害者手帳がなくても、医師の意見で利用できることがあります。
難病のある方も対象になる?
就労移行支援は、厚生労働省が指定する難病の方も対象です。
日常生活に支援が必要と判断された場合、障害者手帳がなくても利用可能です。
難病の種類によっては、診断書や意見書の提出が必要です。
- 厚労省指定の難病が対象
- 手帳がなくても利用できる
- 日常生活に支障があることが条件
- 診断書や意見書が必要になる
たとえば、クローン病の方が、職場復帰を目指して支援を受けた事例があります。
通所開始当初は体力も不安定でしたが、スタッフと相談しながら徐々に活動時間を延ばしていきました。
結果として、就労移行支援を通じて体調管理とスキル習得が進み、在宅勤務の仕事に就くことができました。
このように、難病のある方でも就職を目指して活用できるのが特徴です。



難病だからと諦めず、利用相談をしてみる価値があります。
医師の診断書が必要な場合の対応
就労移行支援の利用には、医師の診断書や意見書が必要なケースが多いです。
特に、手帳がない場合や症状が安定していない場合に求められます。
相談支援員が書類の準備を手伝ってくれるので安心です。
- 診断書や意見書の提出が必要
- 精神・発達障害の方に多い
- 医師に相談して取得する
- 相談支援員が手続き支援
たとえば、発達障害の方が医師に「就労支援の必要性」を診断書で記載してもらい、無事に申請が通った例があります。
医療機関によっては、診断書作成に時間がかかることもあるので、早めの相談が大切です。
就労移行支援事業所に相談すれば、書類準備の流れも詳しく教えてくれます。
ひとりで悩まず、専門機関のサポートを受けながら進めるのが安心です。
「書類が多そうで不安…」という人ほど、早めに話を聞いてみることをおすすめします。



医師の診断書が必要なときも、支援機関がしっかりサポートしてくれます。
利用までの流れと必要な手続き
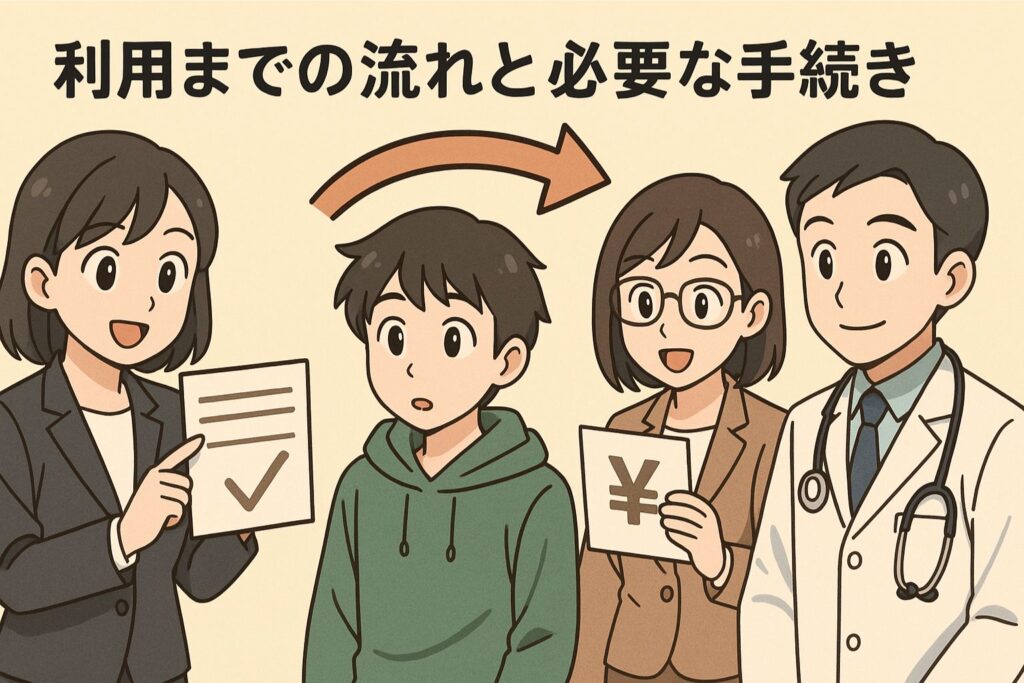
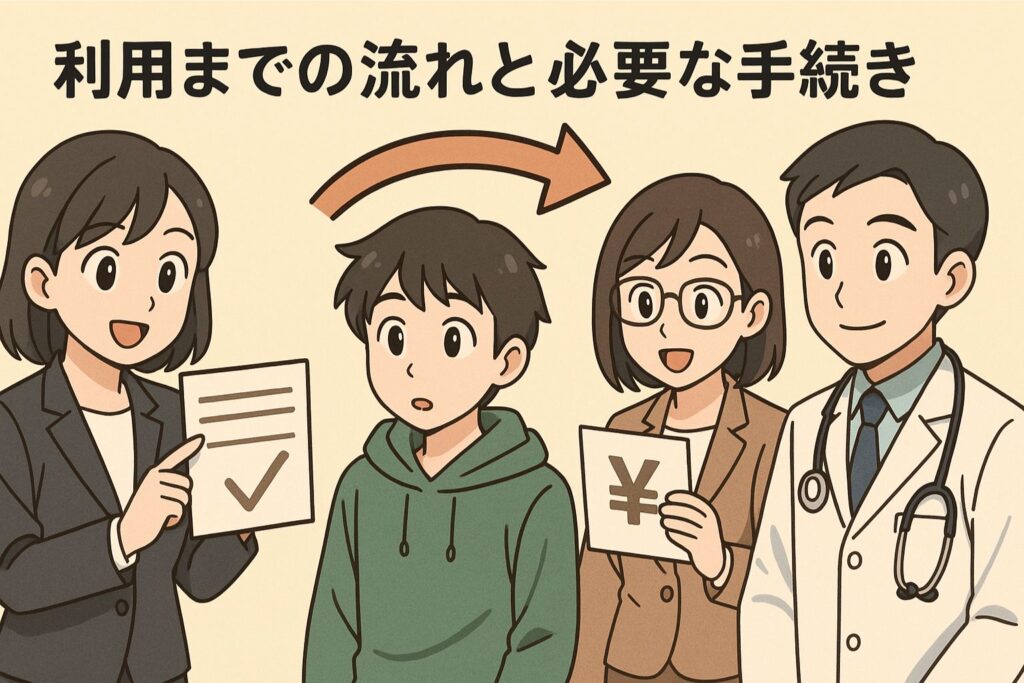
就労移行支援を利用するには、いくつかの手続きと段階があります。
市区町村への相談から始まり、計画書の作成や受給者証の申請が必要です。



少し手続きが多いですが、支援機関がしっかりサポートしてくれるので安心してください。
- 利用開始までの流れ
- 利用料金と自己負担の仕組み
- 支援機関との連携(相談支援事業所、医療機関など)
ここでは、就労移行支援を始めるための手続きや注意点を順番に説明していきます。
実際の手続きの流れを知ることで、不安がぐっと減りますよ。
利用開始までの流れ
就労移行支援を利用するには、まずお住まいの市区町村へ相談することが第一歩です。
その後、相談支援専門員と一緒に「サービス等利用計画」を作成し、受給者証を申請します。
受給者証の交付が決まると、支援事業所との契約をして利用が始まります。
- 市区町村へ相談する
- 相談支援専門員と計画作成
- 受給者証を申請する
- 事業所と契約し利用開始
たとえば、うつ病を持つ方が最寄りの障害福祉窓口に相談し、専門員のサポートでスムーズに申請できました。
その後、1週間ほどで調査を受けた後、受給者証を申請。その後、希望する事業所と契約して利用を開始しました。
書類の準備や手続きはやや複雑ですが、専門員が一緒に進めてくれるので安心です。
まずは「相談」から始めれば、流れに乗って手続きが進みます。



気になる方は、お住まいの市区町村や相談支援事業所に声をかけてみましょう。
利用料金と自己負担の仕組み
就労移行支援は、9割以上の方が無料または低額で利用しています。
サービスは公費で賄われており、所得に応じた自己負担がありますが、多くの人が「自己負担なし」で利用できます。
生活保護受給者や低所得の方は、自己負担ゼロです。
- 多くの人が無料で利用可能
- 負担額は所得で変わる
- 生活保護受給者は全額無料
- 交通費は自己負担の場合あり
たとえば、年収が少ない家庭の方が利用したケースでは、支援費はすべて公費負担となりました。
月額負担額は0円で、サービスの内容も十分に受けられました。
ただし、通所にかかる交通費は支給がない場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。
交通費助成がある自治体もありますので、市区町村の窓口に相談してみましょう。
費用面が心配な方も、まずは支援機関に聞いてみるのがおすすめです。



利用料金はほとんどの人が0円。まずは気軽に相談してみましょう。
支援機関との連携(相談支援事業所、医療機関など)
就労移行支援では、相談支援事業所や医療機関などの支援機関との連携がとても大切です。
利用者一人ひとりの状況をふまえて、複数の専門職が支援計画を作ります。
相談支援専門員が窓口となり、必要な支援や手続きを調整してくれます。
- 相談支援員が手続きをサポート
- 医師の意見書と連携する
- 事業所と情報共有ができる
- 本人の希望を反映した支援
たとえば、発達障害の方が、主治医と支援事業所、相談支援員の三者で面談を行いました。
医師からのアドバイスをもとに、訓練の内容を調整し、無理のない範囲でステップアップできるようにしました。
その結果、本人の負担が少なくなり、自信を持って通所を継続できました。
こうした連携があることで、安心して支援を受けられる体制が整っています。
「病院と福祉、バラバラで不安」という方にも、連携体制がしっかりしています。



相談支援員が医療と福祉をつなぐので、手続きも安心して進められます。
就労移行支援を受けるメリットと提供されるサービス


就労移行支援を受けることで、働くための準備や就職活動をサポートしてもらえます。
生活リズムやビジネスマナー、パソコンスキルなど幅広い内容に対応しているのが特徴です。



ひとりじゃ難しいことも、支援があればできるようになりますよ。
- 就労支援の具体的な内容
- 職場実習や企業とのマッチング支援
- 定着支援まで受けられる安心感
ここからは、具体的にどんな支援が受けられるのかを順番に紹介していきます。
「自分に合うかな?」と悩んでいる人も、支援内容を知れば前向きになれるはずです。
就労支援の具体的な内容
就労移行支援では、生活リズムを整える練習や、働くためのスキルを身につける訓練が行われます。
ビジネスマナー、パソコン操作、履歴書の書き方、面接練習など、就職活動に必要な準備がすべて含まれています。
本人の目標や希望に応じて、訓練の内容を柔軟に組み立ててくれます。
- 生活リズムの改善支援
- ビジネスマナー・PC訓練
- 就職活動のサポート
- 面接練習や履歴書添削
たとえば、睡眠障害のある方が、昼夜逆転の生活から徐々に通所時間を整えていきました。
スタッフと相談しながら、毎日決まった時間に起きて通う習慣を身につけました。
PC訓練ではタイピング練習や表計算ソフトの基本操作を学び、自信がつきました。
就職活動では履歴書の添削や模擬面接を受け、安心して企業に応募できました。



このように、働く前の準備をトータルで支援してくれます。
職場実習や企業とのマッチング支援
就労移行支援では、実際の職場で働く体験ができる「職場実習」も用意されています。
企業とのマッチングも行っており、本人の適性に合った職場を一緒に探してくれます。
企業と連携して、障害への理解を深めてもらう支援も行います。
- 職場実習で働く体験ができる
- 企業と連携して求人紹介
- 適性に合った職場を提案
- 職場との調整や同行も対応
たとえば、ASD傾向のある方が、職場実習で倉庫作業を体験しました。
事前に仕事内容を丁寧に確認し、支援員が一緒に見学にも同行しました。
実習では本人の特性に合った業務に配慮され、ストレスなく作業ができました。
企業側も支援機関から特性についての説明を受け、受け入れ体制が整いました。
実習後、同じ職場にそのまま採用され、安心して働き始めることができました。



適性が合うと、仕事は楽しくなりますよ!
定着支援まで受けられる安心感
就職が決まったあとも、就労移行支援では「定着支援」が受けられます。
職場での悩みや不安に対応し、長く安定して働けるようにフォローしてくれます。
本人だけでなく、企業との間に入って調整する役割も担います。
- 就職後の悩みに対応してくれる
- 企業との調整もサポート
- 定期的な面談で不安を減らす
- 働き続けるための支援がある
たとえば、発達障害の方が、就職後に職場の人間関係で悩みを抱えていました。
支援員が企業と本人の間に入り、働きやすい環境づくりをサポートしました。
定期的に面談を行い、状況を共有しながら少しずつ問題を解消できました。
その結果、本人も安心して仕事を続けることができました。
定着支援があることで、「働き続けること」に自信を持てるようになります。



就職した後も、支援が続くから安心して働けますよ。
利用者の声・支援事例から見る成功のヒント


実際に就労移行支援を利用して就職につながった方々の事例は、これから利用を考えている人にとって大きなヒントになります。
障害の種類や状況は違っても、支援を受けて一歩ずつ前に進んだ例がたくさんあります。



実際の体験談は、自分の未来をイメージするのにとても役立ちますよ。
- ウェルビーの事例
- ミラトレの事例
- マナビーの事例
ここからは、3つの事業所の事例を紹介しながら、どのように支援が役立ったかを解説していきます。
「こんなふうに進めばいいのか」と、自分の道筋の参考になります。
ウェルビーの事例
ウェルビー町田市役所センターの事例です。
Google map
私は2年通いましたが、最初のころは、気持ちが不安定で、なかなか通うことができなかったですが、親身に自分の将来を考えてくれて、一生懸命応援してくれました。
自分が志望動機に迷っているときも、松下さんが、一緒になって考えてくれたことが心強かったです。
ここに通えることができて、本当に良かったと思っています。
ミラトレの事例
ミラトレ横浜の事例です。
Google map
以前利用していた者です。
私は就職までに色々とお世話になったのでミラトレを応援してるので書きます。
ミラトレのスタッフの皆さんはあったかくて、いつでも相談できる人達ばかりでした。
私にとっては信頼をおけるところです。
時期によってずっと同じ人がいる訳でもなく、入所者さんも色が変わっていくので、みんなと話すのが楽しくて私は居心地が良かったです。
ここに来ようとしてる方は、1人で悩んでしまう癖が多い人もいるかもしれませんが、いつでも安心して相談できるスタッフがいるので、悩み事の解決方法を定期的な面談で提示してくれます。
親身になって就職するまでから、就職した後もサポートしてくれますので心強いです。
実際に足を運んでみてください。 参考になったら幸いです。
マナビーの事例
マナビー大宮事業所の事例です。
支援員の皆様、とても親切で障害に理解のある方々ばかりです。
ここに入所して、生活リズムの改善から就職に至るまで全面的にサポートして頂きました。
とてもおすすめの就労移行支援事業所です。



成功事例からわかるのは、「自分に合う働き方」があれば、誰でも前に進めるということです。
自分が対象か判断できないときの相談先とチェック方法


「自分が本当に就労移行支援を利用できるのか分からない」という人も多くいます。
そんなときは、専門機関に相談したり、無料で見学や体験をすることで判断材料が得られます。



まずは聞いてみるだけでOK!行動することで不安が減りますよ。
- 就労移行支援事業所・地域障害者職業センターに相談
- 無料相談・見学で分かること
- 利用前にできる「就労支援の中立的な紹介機関」
ここでは、自分に合う支援を見つけるための相談先やチェック方法を紹介します。
まずは「聞いてみる」「見てみる」ことから始めましょう。
就労移行支援事業所・地域障害者職業センターに相談
就労移行支援の対象かどうかを確認するには、就労移行支援事業所や地域障害者職業センターでの相談が効果的です。
専門の職員が、あなたの状況や希望に合わせて適切な支援を案内してくれます。
福祉の制度についても詳しいので、安心して相談できます。
- 専門スタッフが対応
- 無料で相談できる
- 利用対象か判断してもらえる
- 他の制度も紹介してくれる
たとえば、働きたいけど障害者手帳がない方が、地域障害者職業センターに相談しました。
医師の診断書があれば利用できると説明を受け、就労移行支援の紹介を受けることができました。
その後、手続きを進めてサービスの利用を開始。就職までスムーズにサポートを受けられました。
このように、まずは相談することで、道が開けることがあります。



不安なままひとりで悩まず、専門機関の力を借りましょう。
無料相談・見学で分かること
就労移行支援事業所では、無料の見学や相談会を行っているところがほとんどです。
実際の雰囲気を見たり、スタッフと話すことで、自分に合っているかを判断できます。
予約は簡単で、電話やWEBから申し込めます。
- 事業所の雰囲気が分かる
- 訓練内容の説明を聞ける
- スタッフと直接話せる
- 利用までの流れも相談できる
見学した方の多くが「思っていたよりも安心できた」と感じています。
たとえば、精神障害のある女性が見学後に不安が減り、週1日の通所からスタートできました。
見学をきっかけに、「ここなら続けられるかも」と感じられたそうです。
気になる事業所があれば、まずは一度足を運んでみるのがおすすめです。



しつこい勧誘もないので、気軽に参加できますよ。
利用前にできる「就労支援の中立的な紹介機関」
どの事業所を選べばいいか迷ったときは、「中立的な立場で紹介してくれる機関」に相談すると安心です。
就労支援センターや自治体の福祉課などが該当します。
営利目的ではないため、公平な情報提供が受けられます。
- 複数の事業所を紹介してくれる
- 比較しながら選べる
- しつこい勧誘がない
- 自分に合った事業所が見つかる
たとえば、発達障害の方が就労支援センターに相談し、3つの事業所を見学。
それぞれの内容や雰囲気を比較して、自分に合う場所を見つけられました。
「自分で選べた」という納得感があり、通所後の継続にもつながりました。
情報を得ることで、選択の幅も広がります。



どこに行けばいいか迷ったときは、まずは中立の相談先に聞いてみましょう。
就労移行支援は総合型と特化型に分けられる。


就労移行支援事業所には大きく分けて「総合型」と「特化型」の2つのタイプがあり、それぞれ支援内容や得意とする分野が異なります。



いきなり通う必要はありません。まずは一歩、小さな行動から始めましょう。
- 総合型の就労移行支援事業所
- 特化型の就労移行支援事業所
総合型は、生活リズムを整えたり、働くための基本的な力を身につけたり、就職活動のサポートを幅広く行うタイプです。
どんな仕事が向いているか分からない人や、まずは毎日通うことから始めたい人に向いています。
一方、特化型は、パソコンやデザイン、プログラミングなど、特定のスキルをしっかり学べるタイプです。
すでにやりたい仕事が決まっている人や、スキルを活かして働きたい人におすすめです。
どちらが良いかは、人それぞれ。自分に合ったスタイルを選ぶことが大切です。
【総合おすすめ】(バランス重視・幅広い支援・就職実績◎)
- ウェルビー
→ 企業就労に必要なビジネススキルを実践的に訓練できる。大手企業就職者多数。 - ココルポート
→ 発達・精神障害に強く、個別支援に特化。生活リズムの安定支援も◎。
ウェルビー(Welbe)|高い就職者を誇る就労移行支援事業所


ウェルビー(Welbe)は、障害者の一般就労をサポートする就労移行支援事業所です。
精神障害、発達障害、知的障害、身体障害など、さまざまな障害を持つ方に対応し、全国に121の事業所を展開しています。
就職支援の実績は非常に高く、2024年度の就職数は1,165名、就職後の定着率も91%とトップクラスの水準です。
ウェルビーでは、個別の支援計画を作成し、ビジネスマナーやPCスキルの習得、職場実習、面接対策など、就職に必要なスキルをトータルでサポート。
さらに、就職後も職場への定着支援を続け、働き続ける力をしっかりサポートしてくれます。
また、希望者にはお弁当支給で生活支援にも配慮しています。
まとめ|ウェルビーはこんな人におすすめ
- 事務職や未経験職種にもチャレンジしたい方
- 個別に手厚いサポートを受けたい方
- 精神障害・発達障害など特性に合った支援を受けたい方
- 高い就職率・定着率の実績がある事業所を選びたい方
ココルポート(cocorport)|個別支援にこだわっている就労移行支援事業所


ココルポート(cocorport)は、首都圏・関西・東海・福岡等にに81の事業所を展開しています。
就職者数は、2023年度が762名、累計4,803名、さらに就職後の職場定着率は90%以上という高い実績を誇ります。
ココルポートの最大の特徴は、「個別支援に徹底的にこだわっている」ことです。
利用者一人ひとりの特性や希望に合わせたオーダーメイドの支援プログラムを提供し、安心して訓練に取り組むことができます。
また、経済的な不安を抱える方でも安心して通えるよう、昼食支給や交通費補助といった支援制度も整備されています。
まとめ|ココルポートはこんな人におすすめ
- 発達障害・精神障害に特化した支援を受けたい方
- 高い職場定着率を重視したい方
- 個別に寄り添ったサポートを希望する方
- 就職後も安定して働き続けたい方
【特化型おすすめ】
- Neuro Dive(ニューロダイブ)
→ Web制作・デザイン・プログラミングなど、IT系スキル習得に特化したカリキュラム。 - マナビー
→ 個別支援型、リモート対応。資格取得やPCスキル強化も可能。自宅訓練を希望する人向き。 - キズキビジネスカレッジ
→ 短期集中型カリキュラム。最短での就職・資格取得を目指す方におすすめ。 - ミラトレ
→ 大手転職エージェントdodaと連携。就職率・定着率ともに高く、精神・発達障害特化。 - atGPジョブトレ
→ 発達障害、うつ病、統合失調症など障害特性に合わせた専門コースがある。就職後支援も手厚い。
Neuro Dive(ニューロダイブ)|IT・デザイン分野に特化した就労移行支援


Neuro Dive(ニューロダイブ)は、障害のある方を対象に、IT・デザイン分野での就職を支援する特化型の就労移行支援事業所です。
主に発達障害・精神障害のある方を対象としており、全国に5拠点を展開しています。
Neuro Diveの大きな特徴は、
- Webデザイン
- プログラミング(HTML、CSS、JavaScriptなど)
- グラフィックデザイン(Photoshop、Illustratorなど)
- 動画制作(Premiere Proなど)
といったクリエイティブ・ITスキルに特化したカリキュラムを学べること。
卒業生の80%以上が希望するIT・クリエイティブ系職種への就職を達成しています。
また、企業実習を積極的に行い、実務経験を積んだ上での就職活動ができる点も強みです。
さらに、「週1日から在宅訓練も可能」で、自分のペースで学びながらスキルを身につけることができます。
まとめ|Neuro Diveはこんな人におすすめ
- Web制作、デザイン、プログラミングなどITスキルで就職したい方
- 発達障害・精神障害があり、自分の得意分野を活かしたい方
- 在宅訓練や柔軟な学び方を希望する方
- 実務に直結するスキルを身につけたい方
manaby(マナビー)|在宅訓練もできる柔軟な就労移行支援


manaby(マナビー)は、障害のある方を対象に、在宅訓練も可能な柔軟なスタイルを提供する就労移行支援事業所です。
精神障害・発達障害・知的障害・身体障害など、幅広い障害種別に対応し、主に東北・関東・関西地方を中心に全国約29拠点を展開し、これまで2,159名のサポートしてきました。
大きな特徴は、
- 体調にあわせて「在宅で学ぶ」「通所で学ぶ」を選ぶことができる
- 1500以上の動画から事務やデザイン、プログラミングなど幅広いITスキルが学べる
- 周りを気にせず自分のペースで学べる
という「自由度の高い訓練スタイル」です。
在宅就労定着率96.6%と特に在宅ワークに安定した成果を出しており、就職後の定着支援にも力を入れています。
「外出が不安な方」「通所が難しい方」でも、在宅訓練からステップアップして一般就労を目指せる仕組みが整っているため、 コミュニケーションに苦手意識が強い方も安心です。
まとめ|manabyはこんな人におすすめ
- 通所が難しいため、在宅で訓練を始めたい方
- 自分のペースで学習・就職活動を進めたい方
- 精神障害・発達障害があり、外出に不安がある方
- 働くためのPCスキルを身につけたい方
キズキビジネスカレッジ(KBC)|最短3カ月で一般就労を目指す特化型就労移行支援


キズキビジネスカレッジ(KBC)は、障害のある方を対象に、ビジネススキルの習得に特化した就労移行支援事業所です。
精神障害、発達障害、知的障害など、さまざまな障害に対応し、東京都・神奈川県・大阪府などに事業所を展開しています。
最大の特徴は、
- 「最短3カ月での就職」を目指す短期集中型支援
- ビジネススキルに特化した専門カリキュラム(Excel、会計、英語、資料作成スキルなど)
- 「週5日・1日6時間」の本格的な訓練体制
という点にあります。
就職まで通常約1年半かかるところ平均4か月で就職内定と、一般的な就労移行支援(平均1年~2年)より圧倒的に早く、うつの経験者や発達障害の当事者で初任給38万円の人もいます。
短期間でビジネススキルを身につけ、「できるだけ早く社会復帰・再就職したい」というニーズに特化した支援を行っています。
まとめ|キズキビジネスカレッジはこんな人におすすめ
- 短期間(最短3カ月)で就職を目指したい方
- ビジネススキルを重点的に磨きたい方
- 高い意欲があり、週5日の訓練にしっかり取り組める方
- 精神障害・発達障害でキャリア再スタートを目指したい方
ミラトレ|大手パーソルグループ運営の就労移行支援


ミラトレは、障害のある方を対象に、一般企業への就職を支援する就労移行支援事業所です。
運営は、総合人材サービス大手のパーソルグループ(dodaやanなどを手掛ける企業)が行っています。
精神障害、発達障害、知的障害、身体障害、難病など幅広く対応し、全国に約15拠点を展開しています。
ミラトレの最大の特徴は、
- doda(転職サイト・エージェント)との連携による豊富な求人情報
- 企業実習型プログラムの充実
- 就職率95%超
という、就職直結型の支援体制です。
ビジネスマナー、PCスキル、グループワーク、企業実習などを通じて、即戦力としてのスキルを身につけることを重視しており、就職後も職場定着支援を手厚く行っています。
また、ミラトレは就職後の半年定着率が97%と、全国平均(約60%)を大きく上回る高水準を誇ります。
まとめ|ミラトレはこんな人におすすめ
- できるだけ早く一般企業に就職したい方
- 大手企業・上場企業への就職も視野に入れたい方
- 企業実習を通じて実践的な経験を積みたい方
- 定着支援までしっかりしている事業所を選びたい方
atGPジョブトレ(アットジーピージョブトレ)|障害特性別コースで専門支援


atGPジョブトレ(アットジーピージョブトレ)は、障害のある方を対象に、障害特性別コース制で支援を行う就労移行支援事業所です。
運営は、障害者向け転職サービスで有名なatGP(ゼネラルパートナーズ)。
対象としている障害種別は、
- 精神障害(うつ症状など)
- 発達障害(ADHD・ASDなど)
- 統合失調症
- 聴覚障害
その他身体障害など幅広いですが、それぞれに専門コースが用意されているのが最大の特徴です。
例えば、
- うつ症状に特化した「ジョブトレうつ」
- 発達障害に特化した「ジョブトレ発達障害」
- 聴覚障害に特化した「ジョブトレ聴覚障害」
など、障害ごとの特性に合わせた支援プログラムを提供しています。
2022年度実績では、就職率97%(※※2023年4月~2024年3月の就職データ)就職後半年定着率91.4%という高い成果を出しており、定着支援も手厚いです。
